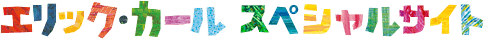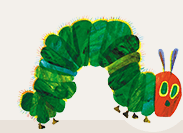日本語版『はらぺこあおむし』の編集者による、エリック・カール氏との思い出
『はらぺこあおむし』は、
1976年に日本語版が出版されました。
その編集を担当した、元編集者による、
エリック・カールさんとの思い出や
絵本刊行の経緯をご紹介します。
想いだすカールさんの横顔
偕成社 元編集者 西野谷 敬子

エリック・カール絵本美術館開館の時に(2002年)
エリック・カールさんと偕成社の出会い
偕成社ではこれまで、エリック・カールさんの創作絵本のほとんどを翻訳刊行しているが、カールさんとのおつきあいは、“The Very Hungry Caterpillar”(『はらぺこあおむし』の原書)のアメリカ刊行時にまでさかのぼる。


本書は、今となっては世界的なベストセラー絵本として知られているが、カールさんが作・絵ともに手がけた作品としてはまだ2作目、新人作家の絵本という立ち位置にあった。
当時、カールさんがつくったダミー本を手にした担当編集者アン・ベネデュースさんは、頭を悩ませていた。斬新なしかけを含んだこの絵本は、複雑な製本作業を必要とするため、経費高になり、アメリカでは製作を引き受けてくれる製本所が見つからなかったのだ。
その件を、ベネデュースさんが来日時に偕成社の当時の専務、今村廣(2代目社長)に相談したところ、今村は、東南アジアで玩具絵本の製作経験のある製本所に相談するよう提案した。
こうして、日本で印刷・製本された本が、1969年にアメリカで刊行されたのだった。
しかし、アメリカ版と同時に、偕成社でもすぐ日本語版を出版することを約束したわけではなかった。
むしろ、編集部では、ベネデュースさんが来日時に持参したカール氏の自作第1作目『1、2、3どうぶつえんへ』(※1)の校正刷りに興味をひかれた。カール絵本の特徴である新鮮な発想、構成の完成度に魅力を感じ、まずこの〈数の絵本〉から出版することに決めた。
※1:『1、2、3どうぶつえんへ』
当時注目されはじめていたイタリアのボローニャ国際児童図書展で、グラフィック大賞を授与された絵本。1970年に翻訳出版すると、日本の読者にも歓迎された。

『はらぺこあおむし』については、その後、アメリカで原書を見た〈おはなしきゃらばん〉の石竹光江さん(※2)が買って帰り、日本の子どもたちも大好きになる絵本だと太鼓判をおしたこと、アメリカンスクールの子どもたちにもひっぱりだこの絵本だとわかったことなどを経て、原書の出版から実に7年後、著作権エージェントを通じて日本語出版権を得たのであった。
※2:〈おはなしきゃらばん〉の石竹光江さん
聖心女子大学史学科卒業。小学校教師、お話文庫活動を経て、子どもたちにお話会や人形劇などをする団体〈おはなしきゃらばん〉を創設。日本各地のみならず、東南アジアにもお話活動をひろめた。
『はらぺこあおむし』の翻訳のひみつ

『はらぺこあおむし』の翻訳者は、小学校教諭(のちに日本女子大学・絵本学講師)であり、絵本の作者・歌人でもある、もりひさし先生に依頼した。もり先生には、その数年前に 『チックタック じかんって なあに?』(B.S.グレイク 作 H.ワイス 絵)という、時間をあつかう絵本の名訳をしていただいていたので、安心しておまかせした。

先生は、たとえば冒頭の原文に「月あかりのなかの葉っぱの上の小さなたまご」とあるのを、「おや、はっぱのうえに、ちっちゃな たまご」と、幼い読者が絵の中の大きな月といっしょに卵をみつける視点で表現されるなどし、もりひさし訳ならではの魅力にあふれた日本語版ができあがった。

あざやかな色彩、さりげなく織りこまれた学びの要素、わくわくするストーリーという、絵本の魅力を存分にそなえた『はらぺこあおむし』だが、一点、日本語訳にあたり、悩ましいことがあった。それは、ちょうになる前のあおむしが、「“まゆ”(cocoon)になりました」と表現されていることだった。

「ちょうになるのは、“さなぎ”からではないだろうか? 」
もり先生も編集部でも疑問に思い、カールさんに問い合わせた。(むろん、傍ら昆虫学者に問い合わせ、まれに熱帯地方では、まゆからちょうへ変態する虫もあるとの調べはついていたが)
カールさんからの答えは、「ここは、どうしても“まゆ”としてほしい。英文の“come out of a cocoon”という表現は、子どもが成長して大人になるとか、平凡な人が自分にうち勝ってすばらしい脱皮をとげる――しいては、芸術家が傑作を生みだすという、壮大な想いをこめた表現だから、原文を活かしてほしい。また、“さなぎ(chrysalis)”という英語は発音しにくいし、冷たい響きがあり、印象がよくない」とのことだった。そう望まれては、“まゆ”に決めざるを得なかった。
ところが、出版すると、案の定、日本の親たち、教師たちはだまっていなかった。編集部は原作者の意図を伝えたが、絵柄が「さなぎ」に見えることもあり、読者の気持ちはおさまらない。結果、3刷から、「あおむしは、さなぎに なって なんにちも ねむりました」の表現に変更したのだった。
*
翻訳者のもり先生は、プロモーション活動にもとても協力的で、当時担当されていたNHKの番組「おかあさんの勉強室」で、家庭や園での『はらぺこあおむし』の楽しみ方の実践例を紹介されたり、営業スタッフに同行してこの斬新な絵本の貴重さを説いてまわられた。おかげで、『はらぺこあおむし』の知名度は高まっていった。
1985年、エリック・カールさん初来日!
はじめての自作絵本『1、2、3どうぶつえんへ』を出版して以来、カールさんは『はらぺこあおむし』『たんじょうびの ふしぎなてがみ』『うたがみえる きこえるよ』など、読者を魅了する絵本を次つぎに生みだしていった。日本でも、このエリック・カールという絵本作家はどんな人物か、その創作の秘密はどこにあるのかと、読者や絵本愛好家からの関心が集まっていた。
(いずれも、もりひさし 訳)
1970年代に米国の絵本作家エズラ・ジャック・キーツさん(※1)が3回来日し、読者との交流も好評だったことから、「カールさんもぜひ来日を」との声が編集部に寄せられた。
カールさんとキーツさんは仲良しだったので、日本への関心も共有していたのだろう。カールさんは偕成社の招待に快く応じてくれ、1985年10月、ついに来日された。なんと2週間にわたり、講演会・原画展・子どもたちとの交流会・サイン会と、多岐に活躍された。
※1:エズラ・ジャック・キーツさん(1916〜1983)
絵本『ゆきのひ』でアメリカのすぐれた絵本にあたえられるコルデコット賞を受賞。代表作に『ピーターのいす』や、日本の名俳句に絵をつけた『春の日や庭に雀の砂あひて』(いずれも偕成社)などがある。
子どもの心を即座にキャッチ!
来日にあたって行われた数々のイベントの一つとして、前述の〈おはなしきゃらばん〉の石竹光江さんが主催する東久留米市のお話会への招待があった。
そこに集まった30人の子どもたちの前に登場すると、カールさんはにこにこと手をふって、話しかけた。
「こんにちは! これから、みんなといっしょにお話ししながら、絵をかいてみようか?」
「わーい! かいて! かいて!」と、子どもたちは小おどりして答える。
「みんなの好きな動物を教えてくれるかな?」
「はーい、ネコです」 と、小学生の男の子。
「おじさんも好きだよ。じゃあ、ネコの顔をかくね」
カールさんは、用意された大きな模造紙に、マジックインクでネコの顔だけをかいた。
「わたしは、イヌ。イヌがすきなの」という女の子の幼児の声には、「そうか、じゃ、イヌのしっぽをかこう!」
カールさんは、子どもたちの発言にしたがって、笑顔でうなずきながら、金魚のヒレ、カメのこうら、ウサギの耳と、動物の特徴ある部分をかき加えていく。
子どもの声にすこし間があくと、
「動物園で会った、おもしろい生き物は、いるかな?」と問いかけ、また子どもの大声にしたがって、キリンの首、シカの角、ウシの乳房、ワニの背、コンドルの羽、そしてゾウの鼻とかき加えていった。やがて、いくつもの頭やしっぽのある奇妙な動物がしあがった。ところどころ、赤や青のマジックでえがいた部分もあり、ふしぎな魅力ある生き物だ。
「どうだい? みんなでつくった動物に、名前をつけようか!」
カールさんの呼びかけに、子どもたちは一瞬とまどったようすだったが……「へんなドーブツ!」 「おかしい生き物」 「まぜこぜ ネコちゃん!」 「ごちゃまぜ どうぶつ!」 と、口ぐちにさけんだ。
「どれも、すてきな名前のようだね。いまは、それぞれ自分の気に入った名前をつけておいて、あとでみんなで相談して、とびきりいい名前をつけてやってね。きょうはとても楽しかったよ、ありがとう!」
カールさんは、満足気にほほえんで手をふった。
いつも読者とともに
子どもたちに愛読される絵本を数十冊生み出してきたカールさんは、2002年、アメリカのマサチューセッツ州にエリック・カール絵本美術館を設立された。そのオープニングのあいさつで、絵本に対する自説をこんな言葉でしめくくった。
「太古から人びとは、海辺の貝や夜空の星のまたたきに美しさを見出してきました。そのように、未来の子どもたちにも、絵本を通して地球や宇宙のすばらしさを感じとってほしい。この美術館がその一助になれば、と願っています。」
2017年には、世田谷美術館で行われた〈エリック・カール展〉のために来日された。
偕成社でねぎらいのランチパーティーを設けたときのこと。おもてなしに一社員が書道を披露すると、カールさんは「ぼくにもやらせて!」と長い和紙にさらさらと、にっこり笑ったあおむしくんを描かれた。ごく自然に。


そのあと、「いつもこの時間にはお昼寝しているので」と仮眠をとられ、ぐっすり休まれた。滞日中、ハードなスケジュールをこなされてきた88歳のカールさんのほほえましい姿であった。
2021年春。フロリダの快適な別宅で冬をすごされたカールさんは、そろそろ北のノーサンプトンのお宅にもどられるころかな、と思い、アシスタントのモトコ・イノウエさんあてに、カールさんのお好きな水ようかんやせんべいを少々お送りした。
5月になって、モトコさんから電話が入った。
「カールさんは、水ようかんをとてもおいしそうに召しあがったのよ。でも、その後、病状が思わしくなく、ご家族に見守られて亡くなられたの」
……悲しい報告だった。でも、カールさんは星になっても、宇宙のかなたから世界中の読者をあたたかく見守っているのよね、とお互いに確信しあったのだった。