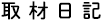2014年3月22日
朝、宿の人の紹介で、近くの家を訪ね、早速家長であるお父さんと交渉をした。彼はこの街で運転手の仕事をしているという。
お父さんは快く取材を了解してくれた。家は本当にホテルから道を下った正面にあり、谷を見渡す崖っぷちに建っている。家にお邪魔すると、たしかに男の子が二人いた。8歳のネリと7歳のラムである。
ネリは物静かでシャイ、ラムは活発で奔放という真逆な性格をもつ兄弟だった。家に現れた突然の闖入者に彼らは少しずつ心を開いてくれるようになった。
ネリとラムと両親の四人と一緒に、お父さんの生家があるゴハン村を訪ねる小旅行に出かけた。お父さんが運転手をしているだけあって、移動は当然車である。しかもただの車ではない。ジープニーと呼ばれる大型車を四人+ぼくで貸し切っての豪華な移動と相成った。

ジープニーは市民の足としてフィリピンの各地で見かけるバスの一種である。ぼくが乗せてもらったジープニーは、乗り心地はよくないが、どんな悪路でも躊躇せずに進んでくれて頼もしい。
バナウェを離れると道が悪くなる。あたりは波のように連なる山々に埋め尽くされていて、およそ人が暮らす集落があるようには思えないのだが、山肌をよく見るとイモなどの野菜を植えた小さな畑や、焼き畑の跡とおぼしき人の手が入った斜面があることに気づいた。イフガオ族はその地形や自然を生かしながら、周辺の山々と広範につきあっている。必要なときに必要な分だけ、山から恵みをもらう。焼き畑も、事前にきっちりと範囲が決められていて、それ以上燃え上がらないようにあらかじめ木々を切り倒すなどの工夫がされている。ぼくのような異邦人には手つかずに見える野山も、イフガオ族にとっては手入れの行き届いた里山であり、自然と人間を繋いでくれる庭園のような存在なのかもしれない。
ジープニーを降りて、棚田の間に作られた細い道を20分ほどひたすら歩いて下っていくと、集落の入口に到着した。これが、人口100人ほどのゴハン村だった。村には、茅葺き屋根の家がいくつかあり、そのうちの一つがお父さんの生家だ。伝統的な高床式の家屋である。
家には女性や子どもたちがいて、ぼくたちを迎え入れてくれた。電気がないので、家の室内は暗い。太陽の光がわずかに射し込んでくるが、その程度である。お母さんは、旦那の生家などに来たことがなかったらしく、なんだかそわそわしている。ネリとラムはそこでも元気に遊び回っていた。その家に暮らしている子どもとも、すぐに仲良くなった。

ネリとラムが遊び疲れた頃、ぼくたちはその家を後にして、バナウェに戻り、眺めのいいレストランで昼食をとった。このあたりの定食は、コンビーフや刻んだ野菜が入った焼きめしの一種や、アドボと呼ばれる炒め物だ。おかずはともかく、棚田からとれた大粒の米は、バナウェのどの店でも食べることができる。ぼくのような米好きにはたまらない場所。
昼食を食べ終わると、あれだけ晴れ渡っていた空に急に灰色の雲がかかりはじめ、やがてどしゃ降りの雨に変わった。足を滑らせながら棚田を見渡すビューポイントに行くも、霧と雨によってほとんど何も見えない。棚田の輪郭を滲ませる雨の中、ぼくは晴れた日の棚田の風景を思い浮かべた。
ネリとラムは家に戻り、シャワーを浴びることになった。が、家に給湯設備はない。だから水道からお湯は出ない。庭のドラム缶に貯められた天水を大鍋で温かくし、それを使って体を洗っていた。ちなみに給湯設備のみならず、ガスコンロもないのでお湯を温めるためには、薪をくべて火をつけねばならない。
バケツ一杯の熱湯をお母さんにかけてもらい、体を洗う二人の兄弟はたくましい。電気はかろうじて通っているので、テレビなどは見られるし、室内も明るい。が、バナウェのような比較的大きな村でも先ほどのゴハン村のように、今も電気なしの生活をおくっている家もある。

このような村でもキリスト教が浸透していて、家の中には小さな祭壇も設けられている。お父さんが若かった頃にはキリスト教もまだそんなにポピュラーではなかったが、今ではほとんどの人が洗礼を受けている。伝統的な農耕儀礼も残ってはいるのだが、ほとんど形骸化しているのが現状だ。
以上、取材の最初の二日間の日記を記した。そんなこんなでネリとラムの家族と日々を過ごし、写真を撮らせてもらい、ようやく本ができあがったのである。バナウェからの帰りはやっぱり冷蔵庫のようなバスに乗って、同じフィリピンとは思えないほど風景が異なる欲望の都市、マニラへとぼくは帰ったのだった。

(写真・文 石川直樹)
世界のともだち⑳『フィリピン 棚田の村のネリ』の詳細はこちらをどうぞ!

-
石川直樹
1977年東京生まれ。高校2年生のときにインド・ネパールへ一人旅に出て以来、2000年に北極から南極まで人力で踏破するPole to Poleプロジェクトに参加。翌2001年には、七大陸最高峰登頂に成功。その後も世界を絶えず歩き続けながら作品を発表している。その関心の対象は、人類学、民俗学など、幅広い領域に及ぶ。著書、写真集多数。2011年、土門拳賞受賞。